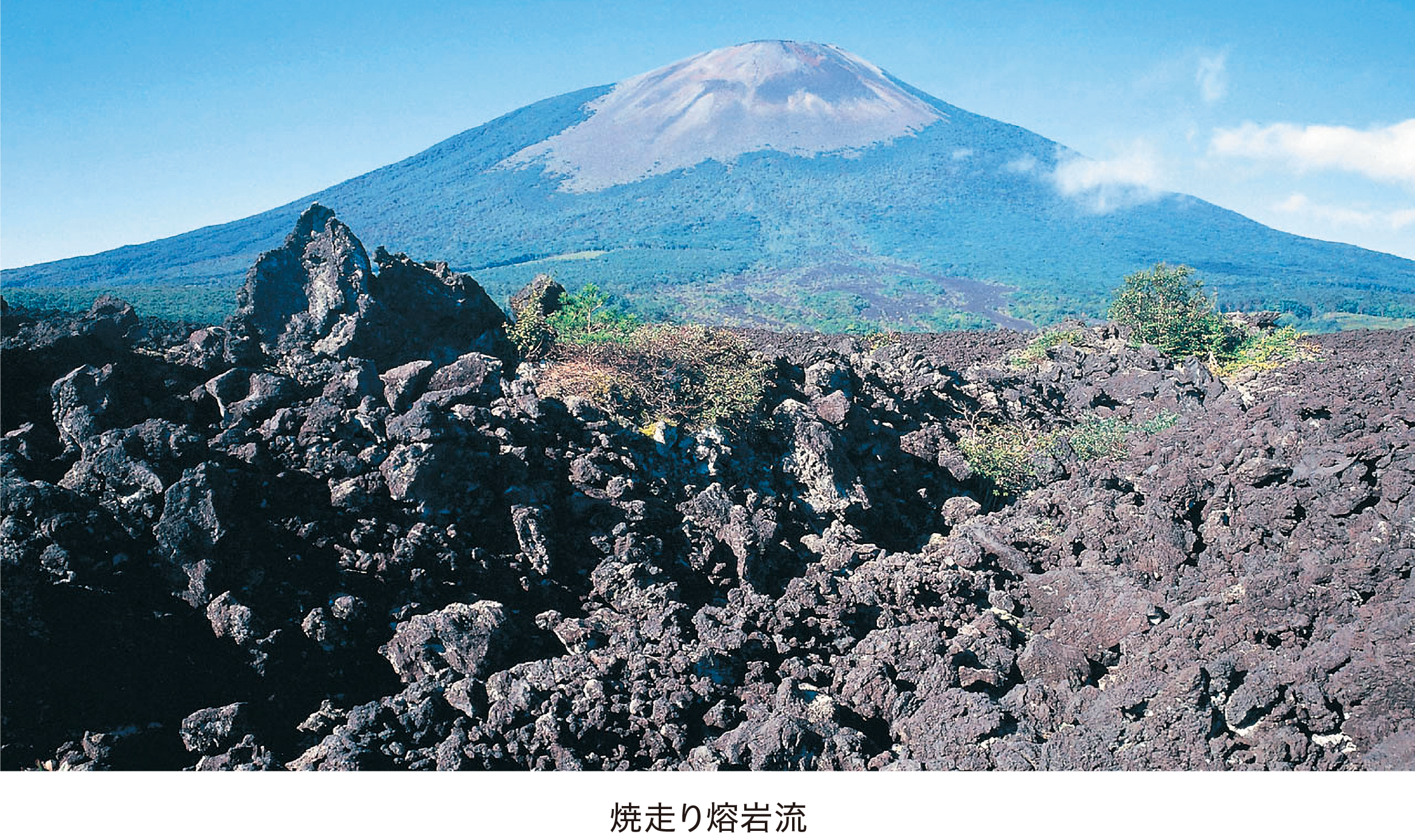地震・津波災害の歴史
岩手県の歴史を語る上で地震津波は避けて通れない。明治29(1896)年の「明治三陸地震津波」、昭和8(1933)年の「昭和三陸地震津波」などは三陸に甚大な被害をもたらした。昭和35(1960)年の「チリ地震津波」からの復興には、戦後初の民選知事である阿部千一が災害復興の道筋を示し、県庁舎やいわて花巻空港の建設、国体の誘致などに取り組んだ。
平成23(2011)年の東日本大震災津波は、県内の死者5,146人、行方不明者1,107人(死者数、行方不明者数は令和6年2月29日時点)という未曽有の大災害であった。県では、東日本大震災津波からの復興を県政の最重要課題と位置付け、国内外から多くの御支援を頂きながら、「安全の確保」、「暮らしの再建」、「なりわいの再生」、「未来のための伝承・発信」を柱に、復興の取り組みを進めてきた。引き続き、新しい三陸地域の創造を目指し、復興のその先を見据えた取り組みを続けている。

災害時や防災教育で活躍した岩手の女性
関東大震災の被災母子救済のため、煙山八重子ら岩手の女性たちによって大正14(1925)年に「愛の家」が設立された。
また、昭和三陸大津波・東日本大震災津波の被災体験を、30年以上紙芝居で語り継いできた田畑ヨシの活動は、防災教育に大きな影響を与えた。